ERCP(内視鏡的逆行性膵管造影)
ERCP(内視鏡的逆行性膵管造影)は内視鏡で胆管と膵管を直接造影する方法。
ERCP(内視鏡的逆行性膵管造影)とは
|
すい臓がん(膵臓癌)の確定診断を行うためには、ERCP(内視鏡的逆行性膵管造影)を行い、 膵内の膵管に直接細いチューブを挿入し、膵臓がんによって生じる膵管の変化を調べます。 その際に、膵液を採取し、がん細胞があるかを検査し、ここでがん細胞が見つかれば、膵臓がんであることを確定診断できます。 しかし、膵臓がんがあったとしても細胞を採取できない場合があり、膵臓がんを強く疑う場合は時間をおいて、他の腫瘍マーカーや画像検査を組み合わせながらERCPを行います。 このような検査をおこなっても膵がんの確定診断が行えない場合もあり、画像検査等で限りなく膵臓がんを疑う場合は、開腹して直接膵臓を調べ、組織を採取する場合もあるそうです。 |
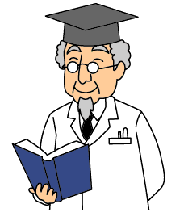
|
ERCPの患者への負担
|
ERCP(内視鏡的逆行性膵管造影)は、すい贈にある小さな癌を見つける可能性が高い精密検査法であるのに違いはありませんが、患者さんの健康状態によっては検査そのものがかなりの負担になるものと思われます。 また、検査を行う専門医の技量というものも患者さんにかかる負担に大きく影響すると言われているので、実際に探し当てるのはなかなか簡単なことではないかもしれませんが、経験の豊富な専門医がいる病院を選んぶことも重要なようです。 |
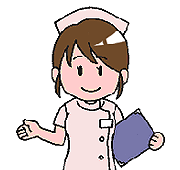
|
|
トランス脂肪 |
【すい臓関連ニュース&トピックス】
生涯のうちで癌であると診断されるおおよその確率のことを「生涯がん罹患リスク」というそうで、がん全般に関しての生涯がん罹患リスクとしては、男性の場合で53%、女性の場合で41%といった統計があります。(2004年のデータ)
この数値は男女共に2人に1人の割合で何らかの癌になるといったことを示しています。
同じ統計データから、すい臓がんでの生涯がん罹患リスクでみてみると男女共に2%となっており、男性の場合ではおよそ51人に1人の割合であり、女性の場合ではおよそ52人に1人の割合で罹患するというようになっているようです。