胆石症
胆汁が結晶を作ることでできた胆石によって誘発される病気の総称。
胆石症とは
|
胆石症とは、何らかの理由で胆汁が結晶を作ることにより結石を作ってしまい、その結石(胆石)によってひきおこされる病気の総称です。 胆汁とは脂肪の消化を助ける消化酵素で、胆汁は肝臓で作られて、胆管という管を通って腸(十二指腸)に分泌されます。 胆石症の主な症状は、右上腹部痛、発熱、吐気、黄疸ですが、胆石を持っていても、8割前後の人は全く症状がないそうです。 また腹痛は食後に現れることが多く、特に生卵や油っこい食品を食べたときに生じやすい傾向があるといわれています。 胆石症によって胆汁が膵管に逆流すると、膵管の粘膜を破壊して膵炎が起こります。 |
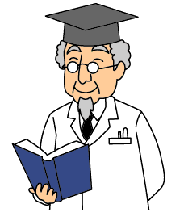
|
胆石症の手術
|
胆石があるといっただけでは基本的に手術の必要はないのですが、胆石が胆のうの出口に詰まって「胆嚢炎(たんのうえん)」を生じている場合には手術を行うことを勧められるケースが殆どです。 現在は胆嚢結石の手術をする場合、従来の開腹手術に替わって腹腔鏡手術にて行うのが主流となってきており、入院期間も短くて済むことが殆どですし、傷跡や痛みも少ないことがメリットとして挙げられます。 |

|
|
たばこ外箱の健康警告 |
【すい臓関連ニュース&トピックス】
癌という病気に関してはよく「5年生存率」というものがいわれるのですが、これは治療後に癌が完治したかどうかを判断するひとつの目安として用いられているわけですが、当然の事ながら癌の種類によって変わってきますし、同じ癌であっても治療を開始した時点でどの程度進行していたかによっても異なります。
そこで、癌の種類(部位による違い)での生存率を統計的にみてみると、すい臓がんというのは5年生存率が極めて低く、このことからもいかに厄介な病気であるかが窺い知れると思います。
30数年前頃では同じように5年生存率が低かった肝臓がんや肺がんが、その後改善されて向上傾向にあるのに対して、すい臓がんは現在に至っても全くの横ばい状態といえる推移しか示していないといったデータもあり難治性がんの代表といえるのですが、あくまでも相対的な統計であり、医療機関の違いや発見時の進行度によっても差があるので、全く光明がないというワケではないと思われます。