トリプシン
すい臓(膵臓)の膵液に含まれる消化酵素の一種。
トリプシンとは
|
トリプシンはすい臓(膵臓)から分泌され、蛋白質の消化酵素の役割を果たします。 タンパク分解酵素であるトリプシンは、食物中のタンパク質を消化するために十二指腸で活性化され、その役割を果たしますが、 さまざまな原因により膵臓の中でトリプシンが活性化することにより、膵臓を自己消化してしまい膵炎を起こします。 トリプシンは他の消化酵素を活性化し膵炎を悪化させ、慢性膵炎の病態を形成する中心的な役割をしてしまうそうです。 |
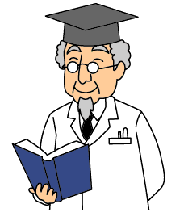
|
トリプシン・インヒビター
|
トリプシン・インヒビターとは、消化酵素であるトリプシンの働きを抑えるトリプシン活性阻害物質のことで、生の大豆に豊富に含まれています。 トリプシン・インヒビターは、トリプシンによるタンパク質分解酵素の働きを阻害することや、膵臓を肥大させるといったことから、以前は身体には悪影響を及ぼすものと考えれていましたが、 一方で体内でインスリンを増加させる作用があるので、糖尿病の治療や予防に役立つといったことで期待されている物質でもあります。 |
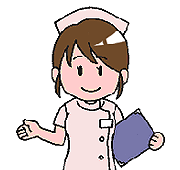
|
|
トランス脂肪 |
【すい臓関連ニュース&トピックス】
女性の乳がんに対する撲滅運動として「ピンクリボン・キャンペーン」というものがあり、最近ではよくさまざまな媒体で見聞きする事が増えましたが、最近はすい臓がんに関する同じような運動があり、「パープルリボン・キャンペーン」と呼ばれています。
ガンの種類の中でも胃がんや肺がん、大腸がんといったものは罹患率も高い事ことから、何かと話題に取り上げられる事も多いので認知度が高いのですが、すい臓がんに関してはまだまだ世間一般に広く知られているとは言い難い現状にあります。
しかしながら、患者さんが年々増加傾向にあることや早期発見が難しく難治性の癌であるということから、このような啓蒙活動により少しでも多くの人にこのガンが認知されることはひじょうに有意義なことであると思います。