CT検査
患者さんの体の周りからエックス線を当てて体内の情報を収集する画像検査。
CT検査とは
|
CT検査とはコンピューター断層撮影のことで、患者さんの体の周りからエックス線を当てて体内の情報を収集し、それをコンピューターを用いて処理して断面図を得る画像検査です。 高速に回転するエックス線発生装置と感知装置により、体の断面を映し出し検査することができます。 最近はCT検査に使用される機器の進歩もめざましく、かなり小さな病変が発見できるようになり、すい臓がん(膵臓癌)の診断にも不可欠な検査法です |
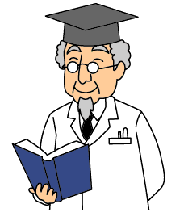
|
CT検査の造影剤
|
CT検査を実施する際には、小さな病変を見つける為とより正確な診断をするために造影剤を使うことがあり、一般的に腕の静脈 から造影剤を注入してからCT検査を始めます。 造影剤を使用することにより患者さんにとっては熱感を生じるなど幾つかの反応を感じる場合があり、アレルギー体質の人などでは、吐き気やおう吐などといった副作用の起こる可能性があります。 ただし、検査前に体質などのチェックを問診されますし、基本的に造影検査を行う医療機関では副作用に対処する準備がされていますので、あまり不安視することもないと思われます。 |
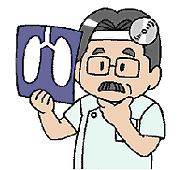
|
|
男性型脱毛症(AGA) |
【すい臓関連ニュース&トピックス】
すい臓がんに限らず、癌という病気は早期発見・早期治療が最も重要ということは誰しも把握されている事と思いますが、すい臓がんは癌の種類の中でも厄介な部類の一つであり、早期発見が難しく進行も速いので、いかに早い段階で診断されるかがその後の治療結果を左右するとよく言われます。
また、すい臓がんは日本で年々増加傾向にあり、男女合わせて年間に2万人以上の方が亡くなられており、厚生労働省が発表している統計(2009年)によると、男性で約1万4千人、女性で約1万2千人以上に上るとなっています。
このようなことから最近では、すい臓がんに関する認知度を高めるなどを目的とした啓発活動が東京、京都、札幌などで開催されたりし始めています。