MRI検査
磁気と電波の力を利用して体の断面や血管を撮影する画像検査です。
MRI検査とは
|
MRI検査とは、X線撮影やCT検査のようにX線を使うことなく、強力な磁石でできたドーナツ状の中に入り、磁気と電波の力を利用して体の断面や血管を撮影する画像検査です。 縦、横、斜めといろいろな方向からの体の断面の写真を撮影することが出来ます。 CTやレントゲン検査と異なり、放射線の被曝がないことがMRI検査の特徴であり、一般的に造影剤を注射することなく検査をするので、患者さんにとっては非常に負担が少ない検査のひとつです。ただし、細かい血管や血流の状態を検査する場合には造影剤を使用することとなります。 |
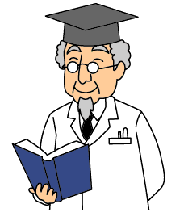
|
CT検査とMRI検査
|
CT検査とMRI検査の違いは、CT検査がX線を用いて撮影するのに対して、MRI検査の場合は磁気の力を用いて撮影します。 また、それぞれの画像診断での特徴により長所・短所があり、骨や肺の状態を診断する場合にはCT検査が得意分野としており、脳の検査などに関してはMRI検査の拡散強調画像で病変を把握しやすいと言われています。 実際の検査時間に関しては個々の検査内容により異なりますが、それぞれ約30分ぐらいで終了する場合が殆どで、MRI検査の方が若干長くなるようです。 |
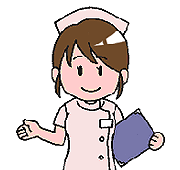
|
|
美容外科ならぬ美容内科 |
【すい臓関連ニュース&トピックス】
すい臓がんを発症するリスク要因としては、糖尿病や慢性すい炎などの他にもあるようで、「喫煙」や「飲酒」も発症リスクと考えられており、特に喫煙はその他の種類の癌と同様に大きな危険因子となるようです。
全く喫煙しない人と比較して喫煙本数の多い人では、すい臓がんの発症が2倍以上多くなるといった統計結果もあるので、すい臓がんに関してだけでなく健康全般のことを考えたうえでも、やはり喫煙は避けるべきだと思われます。
あくまでも統計上の数値と言えばそれまでですが、リスク要因の中でも大きなものの一つといえるのは間違いないのではないでしょうか。