慢性膵炎の検査と診断
血液検査・尿検査・腹部X腺検査・超音波検査(エコー検査)・CT検査・その他
慢性膵炎の検査
|
慢性すい炎(慢性膵炎)の検査には、血液・尿・腹部X腺検査・超音波検査(エコー検査)・CT検査・その他があります。 血液検査の診断としては、 血液中の膵酵素(アミラーゼやリパーゼなど)の値を測定しますが、それら膵酵素の数値の変動も症状と必ずしも一致せず、 診断のきっかけとはなりますが、確診できるほどのものではないとのことです。 慢性膵炎の画像診断としては、超音波やCTなどを用いて膵臓の線維化や膵石の有無を調べますが、画像診断で異常が見つかった時には病態は既にかなり進行している場合が多いといわれています。 |
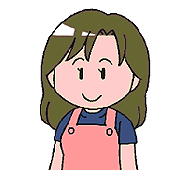
|
慢性膵炎の診断
|
慢性膵炎であるかの診断基準というものが日本膵臓学会によって作成されており、 その慢性膵炎臨床診断基準では、慢性膵炎であるかを診断の確かさの程度により、確診例、準確診例、疑診例の3つに分類しています。 慢性膵炎の早期には膵臓の形や機能に異常が少ないので、早期の慢性膵炎の診断はなかなか困難で、臨床診断基準ではある程度進行したものしか診断できないという問題があるといわれています。 |
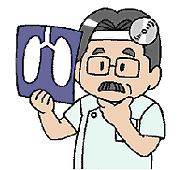
|
【すい臓関連ニュース&トピックス】
女性の乳がんに対する撲滅運動として「ピンクリボン・キャンペーン」というものがあり、最近ではよくさまざまな媒体で見聞きする事が増えましたが、最近はすい臓がんに関する同じような運動があり、「パープルリボン・キャンペーン」と呼ばれています。
ガンの種類の中でも胃がんや肺がん、大腸がんといったものは罹患率も高い事ことから、何かと話題に取り上げられる事も多いので認知度が高いのですが、すい臓がんに関してはまだまだ世間一般に広く知られているとは言い難い現状にあります。
しかしながら、患者さんが年々増加傾向にあることや早期発見が難しく難治性の癌であるということから、このような啓蒙活動により少しでも多くの人にこのガンが認知されることはひじょうに有意義なことであると思います。
|
ファイトケミカルス |