すい炎(膵炎)とは?
すい炎(膵炎)とは、すい臓が炎症を起こした状態のことをいうものです。
病気も欧米化
|
昔に比べると食事や生活様式がすっかり欧米化した日本では、 病気も欧米人に多かった種類のものが増えてきており、すい炎(膵炎)もその一つです。 その原因にはアルコールの多飲や、動物性脂肪の多い食べ物をたくさん摂り過ぎるなど食生活の欧米化が一端を担っているといわれています。 慢性すい炎は年間約3万人の患者さんが治療を行っており、また死亡する危険性がとても高い「重症急性すい炎」では、毎年約1500人の患者さんが発症しているとのことらしいです。 (1994年に行われた厚生省特定疾患難治性膵疾患調査研究班による全国調査より) |
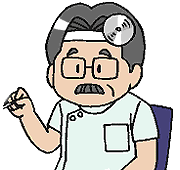
|
すい炎(膵炎)が起こるプロセス
|
すい臓から分泌される消化酵素は、食事から摂取した蛋白質、脂質、糖質などを消化する強力な酵素であり、 その強力な消化酵素によって自らのすい臓を溶かしてしまうのを防ぐために、健康な人のすい臓では生体内で巧妙な仕組みが働いています。 ところが、何らかの理由でその仕組みが乱れて消化酵素がすい臓内で働き出すと、すい臓は自分で分泌した消化酵素によって消化作用を受けてダメージが生じる場合があります。 この状態がすい炎(膵炎)であり、炎症が短期間で急激に起こる「急性すい炎」や、 長期間に渡ってジワジワと起こる「慢性すい炎」に区別されます。 |
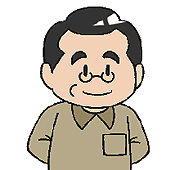
|
【すい臓関連ニュース&トピックス】
つい最近、唾液(だえき)を検査するだけで3種類の癌を発見することができるという画期的とも言える技術が開発されたということが発表され、ひじょうに注目と期待を集めています。
今回開発された技術というのは、採取した唾液に含まれる物質を特殊な装置により解析することで、すい贈がん、乳がん、口腔がんという3種類の癌のいずれかを発症している患者さん特有の物質を見分ける事が可能ということです。
この技術のスゴいところは、唾液を採取するのみという事で患者さんへの負担が極めて少ないという事と発見率にあり、最も低い発見率である口腔がんでさえ80%の確率で、乳がんでは95%、そしてすい贈がんの場合では何と99%の確率で発見することが可能ということです。
|
健康食品に認証マーク |