すい臓がんの検査
すい臓がん(膵臓癌)の検査には血液検査・超音波検査・CT・MRIなどの方法があります。
画像検査などでもなかなか発見しにくい
|
医療機関において膵臓がんの可能性を疑った場合、通常、血液検査として腫瘍マーカーの測定を、 画像検査として腹部超音波検査、腹部CT(コンピュータX線断層撮影)、腹部MRI(磁気共鳴画像)などを行います。 これらの検査は、ほとんど身体に負担を掛けること無く行えますが、これだけしても早期のすい臓がん(膵臓癌)を見つけることは困難な場合も多いようで、 早期のすい臓がん(膵臓癌)の場合、血液検査では全く異常が現れないことも少なくないそうです。 |
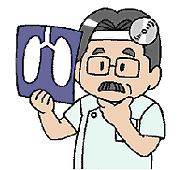
|
内視鏡による検査
|
すい臓がん(膵臓癌)の検査には先に述べた検査方法以外にも、 超音波内視鏡(EUS)や内視鏡的逆行性胆膵管造影(ERCP)などといった内視鏡を用いた検査があります。 内視鏡的逆行性胆膵管造影(ERCP)は、すい臓がんの発見率が高いのですが、 技術的な難しさの他、膵炎などの合併症が起こる可能性もあり、患者さんにとっても負担が大きいなどといった点が挙げられます。 |
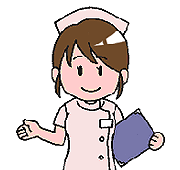
|
【すい臓関連ニュース&トピックス】
ガンの進行度を示すものに「病期(ステージ)」というものがあるということをご存知の方も多いと思われますが、この病期の分類はガンの種類によって異なってきます。
すい臓がんの病期(ステージ)の診断としては、日本膵臓学会の規約による分類もしくは国際的な分類であるUICC分類のどちらかが用いられています。
分類の内容が多少異なるものの、最も早期であるとされる「ステージI」に関してはどちらの場合も、リンパ節への移転がないということと、ガンの大きさが2cm以下で膵臓内にとどまっているといった場合に該当します。
|
トランス脂肪 |