糖尿病と膵臓(すい臓)の関係
すい臓(膵臓)は糖尿病に関係するホルモンであるインスリンを分泌している臓器です。
すい臓で作リ出されるインスリン
|
すい臓(膵臓)は血糖値を調節するインスリン(インシュリン)やグルカゴンというホルモンを作り出し分泌しています。 通常、私たちの血液中には70〜110mg/dL程度のブドウ糖が存在していて、これを血糖といい、その値が血糖値です。 血糖値がほぼ一定に保たれているのは、インスリンやグルカゴンなどのホルモンの調節作用によります。 高血糖状態が慢性化し、持続することによってさまざまな合併症を引き起こすのが、あの厄介な糖尿病です。 |
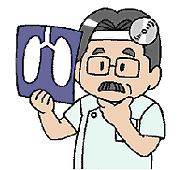
|
ホルモンの調節作用による血糖値の安定
|
通常私たちのカラダでは空腹時には血糖値は下がってきて、これに対応してグルカゴン、アドレナリン、コルチゾールなどのホルモンの分泌が盛んになって、血糖値を上げる方向に働きます。 また逆に、食後などは血糖値が上がってきますが、このときインスリンというホルモンがすい臓(膵臓)から分泌され、血糖値を下げるように働きます。 しかし、なんらかの原因でインスリンの分泌機能そのものが衰えたり、分泌されたとしても作用する力が低下すると高血糖状態になります。 |
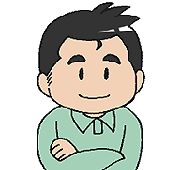
|
【すい臓関連ニュース&トピックス】
すい臓がんというのはガンの中でもひじょうに治療が困難であるとされているのですが、先だって抗がん剤の効果を高める新たな治療法というものが開発されたそうで、すい臓がんに対しても効果が期待できるということらしいです。
その治療法というのは、がん細胞がある周辺の血管を再生するというもので、がん細胞周辺の血管の機能が正常化することで抗がん剤が運ばれやすくなり、その結果として抗がん剤の効き目が得やすくなるとのことです。
まだマウスでの研究結果なので、更なる臨床試験などが必要だと思われますが、大いに期待できる治療法と言えるのではないでしょうか。
|
美容外科ならぬ美容内科 |