膵臓をいたわる食事
すい臓(膵臓)に負担を掛けぬよう、インスタント食品や塩分を多く含む加工品などはなるべく控える。
膵臓をいたわる食事療法
|
料理をするにあたっては、揚げる・炒めるよりは、茹でる・煮る・蒸すといった調理法を選びましょう。 すい臓(膵臓)の炎症により消化酵素の生成、分泌が低下して食物の消化が悪くなるので、消化のよい食品を選びましょう。 基本的に料理の味付けは全体に薄めにしましょう。 インスタント食品などや塩分を多く含む漬物、佃煮、干物、ハム・ソーセージなどの加工品などはなるべく控えましょう。 |
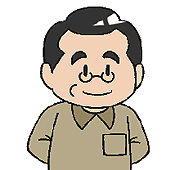
|
ビタミンの補充
|
既に、すい炎(膵炎)や・すい臓がんを患っている場合には、脂肪の制限の食事療法によって、脂溶性ビタミン(ビタミンA・D・E・K)の不足が心配されます。 そのような場合、必要に応じて脂溶性のビタミン(ビタミンA・D・E・K)を補う必要があります。 すい臓(膵臓)を患った場合、これまで述べた食事療法の他に、毎日の生活に於いて過度の疲労やストレスを溜め込まないなど、 規則正しい日常生活を送ることを基本に、きちんと自己管理を行うことが大切です。 |
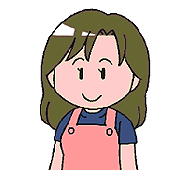
|
|
トランス脂肪 |
【すい臓関連ニュース&トピックス】
癌という病気に関してはよく「5年生存率」というものがいわれるのですが、これは治療後に癌が完治したかどうかを判断するひとつの目安として用いられているわけですが、当然の事ながら癌の種類によって変わってきますし、同じ癌であっても治療を開始した時点でどの程度進行していたかによっても異なります。
そこで、癌の種類(部位による違い)での生存率を統計的にみてみると、すい臓がんというのは5年生存率が極めて低く、このことからもいかに厄介な病気であるかが窺い知れると思います。
30数年前頃では同じように5年生存率が低かった肝臓がんや肺がんが、その後改善されて向上傾向にあるのに対して、すい臓がんは現在に至っても全くの横ばい状態といえる推移しか示していないといったデータもあり難治性がんの代表といえるのですが、あくまでも相対的な統計であり、医療機関の違いや発見時の進行度によっても差があるので、全く光明がないというワケではないと思われます。