脂肪分を摂りすぎない食生活
食事は炭水化物(糖質)中心の低脂肪食とし、必要なカロリーは糖質で補う。
炭水化物(糖質)中心の低脂肪食
|
脂質はタンパク質や糖質に比べ、すい液分泌の刺激となりますので、脂っこい食事を控えるように心掛けましょう。 基本的に食事は炭水化物(糖質)中心の低脂肪食とし、必要なカロリーは糖質で補うようにします。 脂身の多い肉、脂肪分の多いアイスクリーム、スナック菓子類などを頻繁に食べている人は注意が必要です。 すい臓(膵臓)機能に負荷をかけない消化の良い食品を摂るようにしましょう。 |
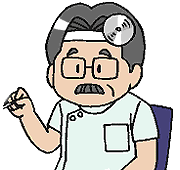
|
刺激の強い食品は避ける
|
刺激物(カフェイン・炭酸飲料・香辛料)は控えるようにしましょう。 刺激の強い食品としては、コーヒー、炭酸系の飲み物、こしょう、わさび、カレー、酸っぱいものなどが挙げられますが、 これらを過剰に摂りすぎるとすい臓に負担をかけてしまいますので注意が必要です。 その他に、タバコに含まれるニコチンが胃酸の分泌を高めて刺激を促すので、喫煙も控えるように心掛けましょう。 |
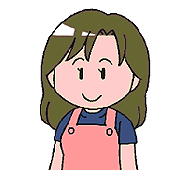
|
|
男性型脱毛症(AGA) |
【すい臓関連ニュース&トピックス】
すい臓がんに限らず、癌という病気は早期発見・早期治療が最も重要ということは誰しも把握されている事と思いますが、すい臓がんは癌の種類の中でも厄介な部類の一つであり、早期発見が難しく進行も速いので、いかに早い段階で診断されるかがその後の治療結果を左右するとよく言われます。
また、すい臓がんは日本で年々増加傾向にあり、男女合わせて年間に2万人以上の方が亡くなられており、厚生労働省が発表している統計(2009年)によると、男性で約1万4千人、女性で約1万2千人以上に上るとなっています。
このようなことから最近では、すい臓がんに関する認知度を高めるなどを目的とした啓発活動が東京、京都、札幌などで開催されたりし始めています。